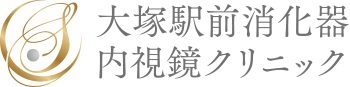ウイルス性胃腸炎とは?

ウイルス性胃腸炎は、感染性胃腸炎の一種で、ウイルスが胃や腸に感染し、嘔吐や下痢といった急性の消化器症状を引き起こす疾患です。一般的に「おなかのかぜ」「はきくだし」「嘔吐下痢症」とも呼ばれ、特に乳幼児や高齢者で発症しやすい傾向があります。代表的なウイルスとして、ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどが知られています。
ウイルス性胃腸炎は、冬季(11月~2月)を中心に流行することが多いですが、ウイルスの種類によっては春先(3月~5月)にも感染者が増加します。症状が激しく、集団感染を引き起こしやすいため、正しい知識を持ち、適切な対策を取ることが重要です。
ウイルス性胃腸炎の原因となる
主なウイルス
ノロウイルス
ノロウイルスは非常に強い感染力を持ち、わずか100個以下のウイルスでも発症することがあります。感染経路としては、汚染された食品(特に加熱が不十分な二枚貝)や、感染者の便や嘔吐物に触れた手指を介した接触感染が主です。
主な症状
- 吐き気・嘔吐
- 水様性の下痢
- 腹痛
- 微熱(発熱は軽度なことが多い)
症状は1~2日で軽快することが多いものの、特に乳幼児や高齢者では重症化しやすいため注意が必要です。
ロタウイルス
ロタウイルスは主に乳幼児に感染し、急性胃腸炎を引き起こします。ノロウイルスと同様に、わずか100個以下のウイルスでも感染が成立し、特に冬から春にかけて流行します。
主な症状
- 水様性の下痢(白っぽい便が特徴)
- 嘔吐
- 発熱
- 腹痛
症状は1~2週間続くこともあり、重度の脱水症状に陥るリスクが高いため、適切な水分補給が重要です。
アデノウイルス
アデノウイルスによる胃腸炎は、特に乳幼児に多く見られます。
主な症状
- 持続的な下痢(1週間以上続くことも)
- 嘔吐(ない場合もある)
- 軽度の発熱
発熱することが少なく、下痢のみが長期間続くのが特徴です。ウイルスが便とともに長期間排出されるため、感染拡大のリスクが高い点にも注意が必要です。
ウイルス性胃腸炎の感染経路
ウイルス性胃腸炎は、主に経口感染で広がります。具体的には、以下のような感染経路が考えられます。
人から人への感染(接触感染)
感染者の手や嘔吐物・便に触れた手を介してウイルスが口に入ることで感染します。
特に、
- トイレの後に手洗いをしない
- 食事の前に手洗いをしない
- 家族や保育園・学校などでの接触
といった場面で感染が拡大しやすくなります。
食品を介した感染
汚染された食品を摂取することで感染することもあります。
特に、
- 生の二枚貝(カキなど)
- 十分な加熱がされていない食品
- 汚染された水や食材を使用した料理
などはリスクが高いため注意が必要です。
環境を介した感染
ウイルスが付着した物や表面を触った手が口に入ることで感染することもあります。
特に、
- ドアノブや手すり
- トイレのレバーや水道の蛇口
- おもちゃや食器類
を介して感染が広がるため、定期的な消毒が有効です。
ウイルス性胃腸炎の治療
ウイルス性胃腸炎に特効薬はなく、抗菌薬(抗生剤)は効果がありません。そのため、治療の基本は 対症療法(症状を和らげる治療) になります。
水分補給

嘔吐や下痢による脱水を防ぐため、少量ずつこまめに水分を補給することが重要です。
特に以下の摂取が推奨されます。
- 経口補水液(OS-1など)
- スポーツドリンク(ただし、糖分が多いため薄めて使用)
- 湯冷まし・薄めたお茶・スープ
食事管理
初期(嘔吐がある時)
無理に食べずに、経口補水液を少しずつ摂りましょう。
症状が落ち着いてきた
 おかゆ、うどん、バナナ、すりおろしたリンゴなど消化に良いものを摂取しましょう。
おかゆ、うどん、バナナ、すりおろしたリンゴなど消化に良いものを摂取しましょう。
避けるべき食品
脂っこいもの、乳製品、刺激物(カフェイン・香辛料)は避けましょう。
安静を保つ
 十分な休息を取り、症状が落ち着くまで無理をしないことが大切です。
十分な休息を取り、症状が落ち着くまで無理をしないことが大切です。
ウイルス性胃腸炎の潜伏期間
ウイルスの種類によって潜伏期間は異なります。
ノロウイルス
24~48時間
ロタウイルス
1~3日
アデノウイルス
3~10日
一般的に、ウイルス性胃腸炎の潜伏期間は 1~3日 ですが、長いものでは 1週間以上潜伏することもあります。