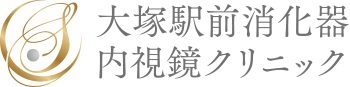口臭の90%は
お口の中に原因がある

口臭の原因の多くは、口腔内の環境にあります。特に歯周病や虫歯、舌苔(舌の汚れ)などが主な要因です。口臭が気になる方は、まず歯科を受診し、適切な治療を受けることが大切です。
しかし、「歯科での治療を終えても口臭が気になる」「定期的に歯科へ通っているのになぜか口臭が改善しない」という方は、実は消化器疾患が関係している可能性があります。
口臭とは?
口臭は、口腔内の細菌が発するガスや食べ物の臭い、さらには胃腸から上がってくるガスなど、さまざまな要因によって発生します。一時的な口臭であれば問題ありませんが、慢性的な口臭が続く場合は注意が必要です。
口臭の種類
生理的口臭
 朝起きた直後や空腹時、緊張した時に口臭が強くなることがあります。これは唾液の分泌量が減少し、口腔内の細菌が増殖して臭いの原因となるためです。通常は、歯磨きやうがいをすることで改善します。
朝起きた直後や空腹時、緊張した時に口臭が強くなることがあります。これは唾液の分泌量が減少し、口腔内の細菌が増殖して臭いの原因となるためです。通常は、歯磨きやうがいをすることで改善します。
飲食物による口臭(外因的口臭)
ニンニク、ネギ、アルコールなど臭いの強い飲食物を摂取した後、一時的に口臭が発生することがあります。これらの臭い成分は胃で消化された後、血液を通じて肺へ送られ、呼気として排出されますが、時間の経過とともに消失します。
心理的口臭
 自分自身で「強い口臭がある」と思い込むケースで、実際には口臭が発生していないにもかかわらず、不安が原因で口臭を気にしすぎることがあります。
自分自身で「強い口臭がある」と思い込むケースで、実際には口臭が発生していないにもかかわらず、不安が原因で口臭を気にしすぎることがあります。
病的口臭
口腔内の問題だけでなく、全身の疾患によって発生する口臭です。
口臭と消化器疾患の関係
ピロリ菌感染と口臭
ピロリ菌に感染すると胃の粘膜が炎症を起こし、慢性胃炎や胃潰瘍の原因となります。この状態では、舌苔の増加や唾液の分泌低下が起こり、腐敗臭のような口臭を引き起こすことがあります。特に「卵の腐ったような臭い」が特徴的です。
便秘と口臭
腸内に便が滞留すると、腸内の悪玉菌が増加し、発生したガスが血液を通じて全身に循環します。その結果、肺からガスが排出され、口臭として現れることがあります。便秘がちの人は、腸内環境を改善することで口臭を軽減できる可能性があります。
肝臓疾患と口臭
肝臓は体内の毒素を解毒する役割を持っています。肝機能が低下すると、アンモニアなどの有害物質が血液中に溜まり、それが肺を通じて排出されることで「カビ臭い」「甘い腐敗臭」のような口臭が発生することがあります。
糖尿病と口臭
糖尿病患者の口臭は、アセトン臭と呼ばれる甘酸っぱい臭いが特徴です。これは、血糖値が高い状態が続くことで脂肪が分解され、ケトン体という物質が増加するためです。
口臭に伴う症状
以下のような症状がある場合、消化器疾患が口臭の原因になっている可能性があります。
胃の不快感や胸やけ
 胃酸の逆流による症状です。
胃酸の逆流による症状です。
食事の際にむせる
逆流性食道炎の影響です。
胃もたれや胃痛
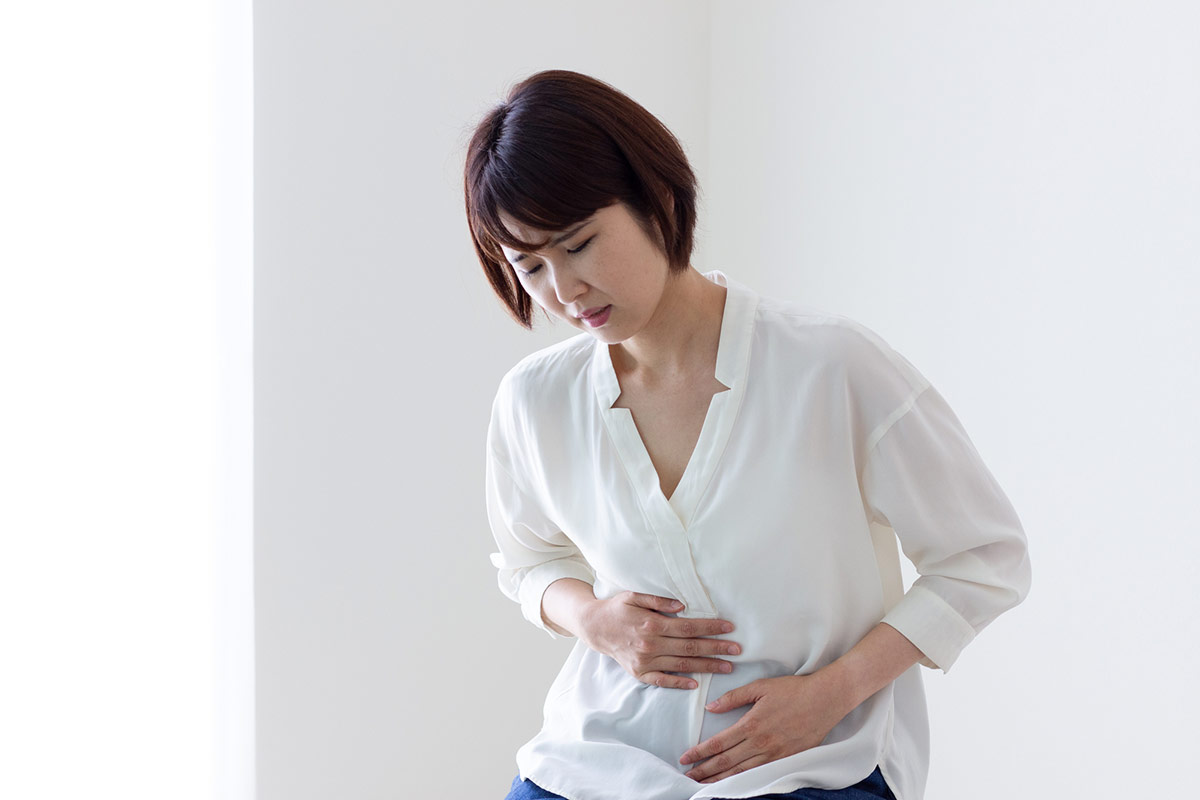 慢性的な胃炎や胃潰瘍の可能性があります。
慢性的な胃炎や胃潰瘍の可能性があります。
食欲不振
胃腸の不調が影響していることが多いです。
口臭の検査と治療
内視鏡検査(胃カメラ・
大腸カメラ)で原因を特定
 口臭が消化器疾患に関連している場合、胃や腸の状態を直接確認することが重要です。当院では、胃カメラや大腸カメラを用いた精密検査を行っています。
口臭が消化器疾患に関連している場合、胃や腸の状態を直接確認することが重要です。当院では、胃カメラや大腸カメラを用いた精密検査を行っています。
胃カメラでわかる疾患
- 逆流性食道炎
- ピロリ菌感染症
- 胃炎
- 胃潰瘍
- 胃がんの有無
大腸カメラでわかる疾患
- 大腸ポリープ
- 大腸がん
- 過敏性腸症候群(IBS)
- 便秘や腸内環境の異常
生活習慣の改善
消化器疾患に起因する口臭を予防するためには、以下のポイントを意識することが大切です。
食生活の見直し
暴飲暴食を避け、胃に負担をかけない食事を心がけましょう。
適度な運動
腸の働きを活発にするため、適度な運動を習慣化しましょう。
ストレス管理
ストレスは胃腸の働きを低下させるため、リラックスする時間を作るようにしましょう。
専門的な治療
ピロリ菌感染が確認された場合は、除菌治療を行うことで口臭の改善が期待できます。また、逆流性食道炎には適切な胃酸抑制剤を使用し、腸内環境の乱れにはプロバイオティクス(善玉菌)を取り入れることが有効です。
口臭でお悩みの方は
当院へご相談ください
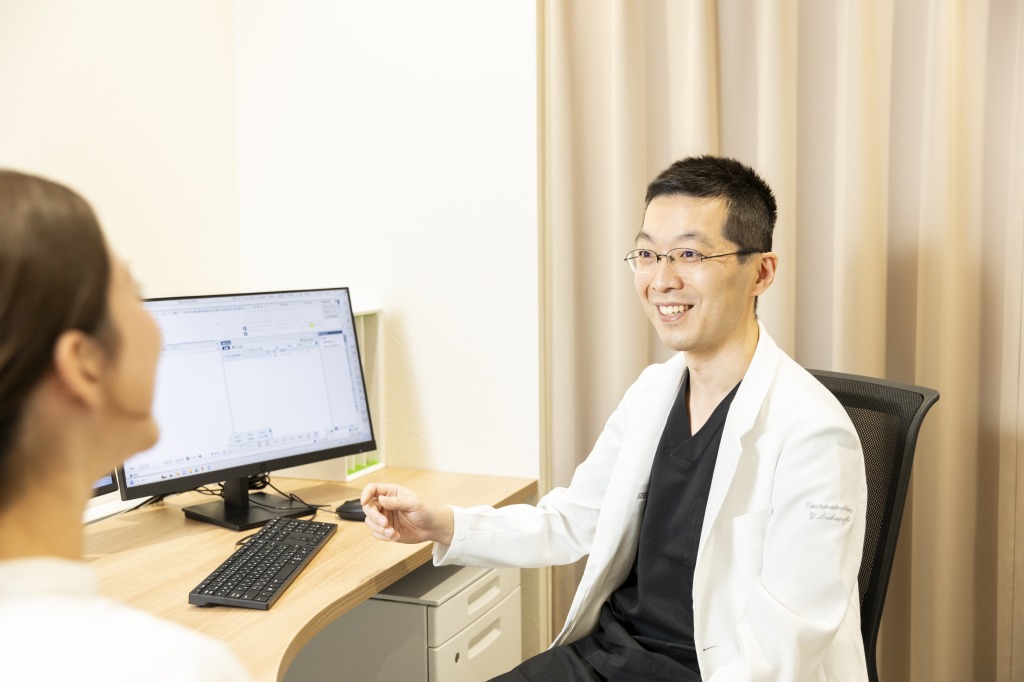
口臭は単なる口腔内の問題ではなく、消化器の健康状態と密接に関係しています。当院では、胃カメラや大腸カメラを活用し、口臭の根本原因を明らかにすることが可能です。
口臭でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。