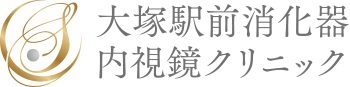呑酸・胸焼けとは?
 呑酸(どんさん)や胸焼けは、多くの人が経験する消化器症状の一つです。これらの症状は、食道に胃酸や胃の内容物が逆流することで発生します。胸のあたりに焼けるような不快な感覚が生じるのが「胸焼け」、酸っぱい液体が口まで上がり、ゲップが出るのが「呑酸」です。症状がひどい場合には、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。
呑酸(どんさん)や胸焼けは、多くの人が経験する消化器症状の一つです。これらの症状は、食道に胃酸や胃の内容物が逆流することで発生します。胸のあたりに焼けるような不快な感覚が生じるのが「胸焼け」、酸っぱい液体が口まで上がり、ゲップが出るのが「呑酸」です。症状がひどい場合には、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。
呑酸・胸焼けを
放置しても大丈夫?

「ただの胸焼けだから」と放置するのは危険です。特に、夜間に胸焼けで目が覚める場合は注意が必要です。これは狭心症や食道がんなどの重大な疾患が隠れている可能性があるためです。制酸薬を服用して症状が緩和されたとしても、根本的な原因を特定するために検査を受けることが重要です。
さらに、長期間にわたる胃酸の逆流はバレット食道のリスクを高めます。バレット食道は、将来的に食道がんへと進行する可能性があるため、適切な検査と管理が求められます。定期的な胃カメラ検査を受け、早期発見・早期治療を行いましょう。
呑酸・胸焼けの症状は?
呑酸や胸焼けは、多様な症状を伴うことがあります。以下の症状が見られる場合は、消化器専門医に相談することをおすすめします。
- 口の中に酸っぱい液体が上がってくる
- 喉や食道に違和感を感じる
- 頻繁にゲップが出る
- 胸の中央が焼けるような感覚がする
- 食後に症状が悪化する
- 喉の奥(食道の奥)に痛みを感じる
- 吐き気や嘔吐を伴うことがある
- 慢性的な咳や声のかすれ
- 口臭が気になる
考えられる原因
(食事や生活習慣による影響)
脂っこい食事や香辛料の摂取
脂肪分や香辛料が多い食事は、胃酸分泌を促進し、逆流性食道炎を引き起こす原因となります。
過食や早食い
大量に食べたり、急いで食べると胃に負担がかかり、胃酸が食道に逆流しやすくなります。
アルコールやカフェインの摂取
 アルコールやカフェインは下部食道括約筋を緩め、胃酸が食道に逆流しやすくなります。
アルコールやカフェインは下部食道括約筋を緩め、胃酸が食道に逆流しやすくなります。
喫煙
喫煙は食道の粘膜を刺激し、下部食道括約筋の機能を低下させ、胃酸が逆流します。
食後すぐに横になる習慣
 食後にすぐ横になると、胃酸が逆流しやすくなるため、注意が必要です。
食後にすぐ横になると、胃酸が逆流しやすくなるため、注意が必要です。
考えられる原因
(消化器疾患や体質的な要因)
胃の機能低下
胃の動きが鈍くなると、食べ物や胃酸が上がりやすくなります。
胃ヘルニア(食道裂孔ヘルニア)
食道と胃の間に異常があり、胃酸が食道に逆流する原因となります。
肥満
腹圧が高くなると、胃酸が逆流しやすくなるため、肥満はリスク要因です。
妊娠
妊娠中はホルモンの変化や腹圧の増加により、胃酸の逆流が起こりやすくなります。
呑酸・胸焼けの検査方法
 胃カメラ検査は、逆流性食道炎やその他の疾患の有無を確認するための有効な検査方法です。食道粘膜の炎症や潰瘍、バレット食道の有無を詳細に観察できます。
胃カメラ検査は、逆流性食道炎やその他の疾患の有無を確認するための有効な検査方法です。食道粘膜の炎症や潰瘍、バレット食道の有無を詳細に観察できます。
当院では、鎮静剤を使用し、ウトウトした状態で楽に検査を受けられるよう配慮しておりますので、ご不安のある方も安心して受診してください。
呑酸・胸焼けの治療方法
呑酸や胸焼けの治療には、薬物療法と生活習慣の改善が重要です。
薬物療法
呑酸や胸焼けの治療には、胃酸分泌を抑制する薬が用いられます。プロトンポンプインヒビター(PPI)やH2ブロッカーは胃酸の過剰分泌を抑えることで、症状を軽減します。また、制酸薬も一時的な緩和を目的に使用されます。重症の場合、胃酸逆流を防ぐ薬や、粘膜を保護する薬も処方されることがあります。
生活習慣の改善
 食生活の改善が重要です。脂っこい食事や香辛料を控え、過食や早食いを避けることで胃への負担を減らします。アルコールやカフェイン、喫煙を控えることも効果的です。また、食後すぐに横にならないこと、適度な運動をすることで、胃酸逆流を予防できます。規則正しい生活を送ることが症状の軽減に繋がります。
食生活の改善が重要です。脂っこい食事や香辛料を控え、過食や早食いを避けることで胃への負担を減らします。アルコールやカフェイン、喫煙を控えることも効果的です。また、食後すぐに横にならないこと、適度な運動をすることで、胃酸逆流を予防できます。規則正しい生活を送ることが症状の軽減に繋がります。